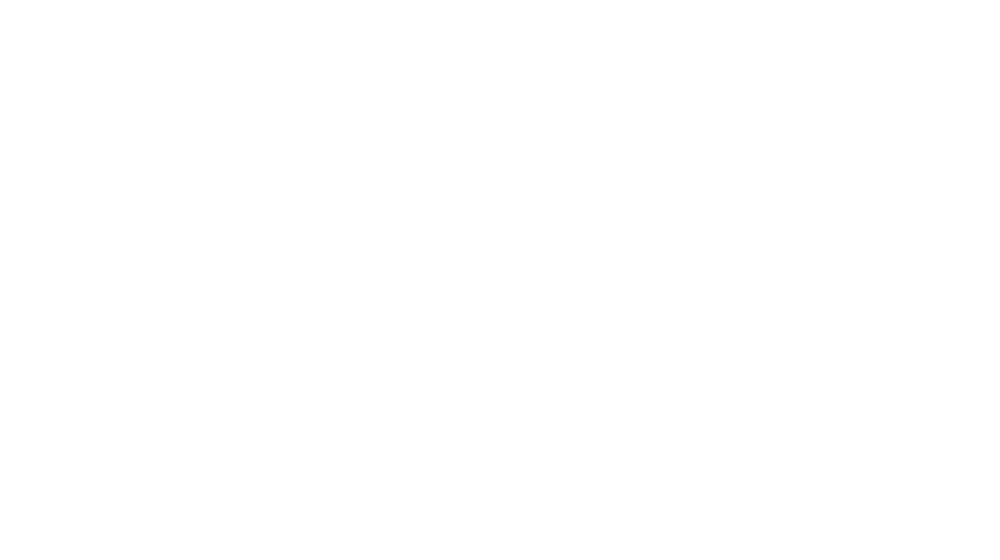28 東京彫金
金属の表面に鏨(たがね)という工具を使って彫刻を施した工芸品。古墳時代後期の装身具・馬具から始まり、武士が台頭すると刀剣・甲冑、江戸時代には、煙管(きせる)や根付などの生活用品にまで彫刻が施されるようになった。格式を重んじる作風である京都風の「家彫(いえぼり)」に対し、墨絵の筆勢を表現した片切彫(かたぎりぼり)を用いた斬新な作風は「町彫(まちぼり)」と呼ばれた。
工芸品目で絞り込む
01 村山大島紬 (1)
02 東京染小紋 (5)
04 江戸木目込人形 (15)
05 東京銀器 (9)
06 東京手描友禅 (5)
07 多摩織 (3)
08 東京くみひも (5)
09 江戸漆器 (5)
10 江戸鼈甲 (3)
12 東京仏壇 (2)
13 江戸つまみ簪 (3)
14 東京額縁 (3)
17 江戸簾 (1)
18 江戸更紗 (3)
19 東京本染ゆかた・てぬぐい (4)
21 江戸衣裳着人形 (1)
22 江戸切子 (30)
23 江戸押絵羽子板 (2)
24 江戸甲冑 (4)
25 東京籐工芸 (8)
26 江戸刺繍 (2)
27 江戸木彫刻 (2)
28 東京彫金 (5)
29 東京打刃物 (10)
30 江戸表具 (1)
31 東京三味線 (4)
33 東京無地染 (1)
35 江戸からかみ (1)
36 江戸木版画 (5)
37 東京七宝 (4)
38 東京手植ブラシ (8)
39 江戸硝子 (6)
40 江戸手描提灯 (1)
41 東京洋傘 (5)
43 その他 (45)